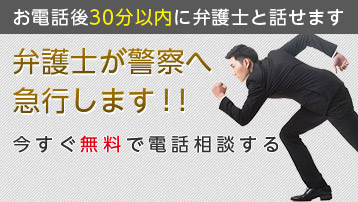起訴・不起訴は誰が決めるの? 逮捕後の流れや不起訴を目指す方法
- その他
- 起訴
- 不起訴
- 誰が決める

家族が逮捕された場合、今後の手続きや起訴・不起訴の判断がどのように行われるのか不安に感じる方は多いでしょう。
犯罪の容疑をかけられ逮捕されてしまった場合でも、証拠が不十分であれば不起訴とされるケースがほとんどです。また、証拠がそろっている場合でも、状況によっては不起訴処分となる可能性はあります。重い刑罰を科されたり前科がついたりするのを避けるためには、不起訴処分を獲得することが重要です。
本コラムでは、起訴・不起訴が決まる流れや不起訴を目指す方法などについて、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士が解説します。


1、起訴・不起訴は誰が決めるの?
刑事事件で逮捕された後、起訴されるか不起訴となるかは、その後の手続きに大きく影響を与えます。では、この重要な判断は誰が行うのでしょうか?
以下では、起訴・不起訴を決める人物や、不起訴処分に関する基礎知識を解説します。
-
(1)起訴・不起訴を決めるのは検察官
刑事事件の起訴・不起訴の判断は、警察ではなく検察官が行います。警察は捜査を担当し、容疑者を逮捕して証拠を集めますが、最終的に起訴するかどうかを決めるのは検察官の役割です。
不起訴処分には、主に次のような種類があります。- 罪とならず
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 親告罪の告訴取り下げ
- 起訴猶予
不起訴処分となると、刑事手続きはその時点で終了します。不起訴になった場合には「前歴」は残りますが、「前科」はつきません。
前歴とは、犯罪の疑いをかけられて捜査対象となった履歴です。前歴が残っても生活への影響はほとんどありませんが、再度被疑者として捜査されたときに処分が重くなる可能性があります。 -
(2)起訴猶予について
「起訴猶予」は、不起訴処分の種類のひとつです。起訴できるものの、被疑者の境遇や事件の軽重・状況などを考慮し、あえて起訴しないと検察官が判断した場合に出されます。
起訴猶予が認められる要因としては、以下のような点が挙げられます。- 被害者と示談が成立している
- 被疑者が十分に反省し、謝罪や賠償を行っている
- 初犯であり、再犯の可能性が低い
起訴猶予になるとその時点で釈放され、前科がつくことも刑罰を受けることもありません。
-
(3)不起訴と無罪の違い
「不起訴」と「無罪」は前科がつかないという点で混同されがちですが、異なる意味をもつ言葉です。
不起訴は検察官によって判断され、不起訴となった場合はその時点で刑事手続きが終了します。不起訴処分の種類には無罪相当の「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」もあれば、「起訴猶予」という有罪相当のものもあります。
対して無罪は、裁判が行われた結果、裁判官が犯罪の成立を認めず被告人に無罪判決を言い渡した場合に成立するものです。不起訴の場合は裁判自体が行われませんが、無罪の場合は裁判が進行した後に判断されるものです。
2、逮捕後に起訴・不起訴が決まる流れ
逮捕後の手続きは厳格に決められており、一定の期限内に起訴するか不起訴とするかが判断されます。逮捕から起訴・不起訴が決定するまでの流れについて、以下で段階別に確認していきましょう。
-
(1)逮捕後48時間以内:警察による取り調べと送致
被疑者として逮捕されると留置場に入れられ、警察による取り調べが行われます。
取り調べの主な目的は、事件の詳細を把握し、証拠を収集することです。取り調べで話した内容は証拠として扱われる可能性があるため、慎重に対応しなければなりません。
警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察に送致するかどうかを判断します。送致されない場合は釈放され、事件は終了となります。 -
(2)送致後24時間以内:検察官による取り調べと勾留請求
送致が決定すると事件は警察から検察へ移され、検察官による取り調べが行われます。検察官は警察から受け取った情報と取り調べで得た情報をもとに、勾留請求するかどうかを判断します。
勾留とは、被疑者または被告人が逃亡したり証拠隠滅したりするのを防ぐために、逮捕に引き続き身柄を拘束することです。
送致後24時間の期限内に、裁判所への勾留請求もしくは釈放の決定が行われます。 -
(3)勾留期間:最大20日間
勾留請求が行われ裁判官が勾留を認めた場合、被疑者は原則として10日間勾留されます。ただし、捜査が十分に進んでいない場合はさらに10日間(合計で最大20日間)延長される場合もあります。
勾留が決まると逮捕から最大で23日間身柄が拘束されることになるため、注意が必要です。
勾留中は引き続き取り調べが行われ、捜査が進められます。留置場では連絡の自由は制限されますが、接見禁止がつかなければ家族や友人との面会は可能です。 -
(4)起訴・不起訴の判断
勾留期間が終了する前に、検察官は最終的に起訴するか、不起訴とするかを決定します。
起訴される場合、被疑者は被告人となり、正式に刑事裁判が始まります。一方、不起訴になった場合は釈放され、裁判にはかけられず前科もつきません。
また、勾留期間中に起訴・不起訴の判断がつかず、「処分保留」として釈放されるケースもあります。 -
(5)起訴されると刑事裁判が開始
起訴されると、刑事裁判の手続きが進められます。起訴の種類は、主に「正式起訴」と「略式起訴」の2つです。
正式起訴は「公判請求」とも呼ばれる通常の起訴で、公開の法廷で裁判が進められます。一方、略式起訴は一定額以下の罰金刑(あるいは科料)を言い渡す簡易的な起訴で、書類の審理のみで処分が決まります。
正式起訴されると、最終的な判決が出るまで刑事手続きが続くことになり、前科がつくのを避けるには無罪判決を得なければなりません。起訴後に無罪判決を獲得するのは非常に困難であるため、起訴を避けるための対策が重要となります。
お問い合わせください。
3、逮捕後に不起訴を目指す方法
逮捕された後、仕事や生活への影響を最小限に抑えるためには、不起訴処分を目指す必要があります。不起訴を目指すにあたってできることは、以下のとおりです。
-
(1)被害者と示談する
不起訴処分を得るためには、被害者との示談を成立させることが重要です。示談とは、被害者と加害者が話し合い、損害の賠償や謝罪などを条件に合意し和解することを指します。
示談が成立すると、すでに当事者間で和解している証明となり、検察官が起訴を見送る可能性が高くなります。被害者がいる事件では被害者の処罰感情も起訴・不起訴の判断に影響するため、示談が不起訴の決め手となる場合もあるでしょう。
ただし、示談交渉はデリケートな問題であり、被害者の感情や意向を尊重しながら進める必要がある点に注意が必要です。 -
(2)被害者との示談で検討すべきこと
示談をして不起訴処分を得るためには、被害者に対して適切な損害賠償を支払うことが重要になります。損害賠償の内容には、以下のようなものがあります。
- 治療費や通院費(傷害事件など)
- 盗まれた金品の返還(窃盗・詐欺など)
- 精神的苦痛に対する慰謝料
適切な額の損害賠償を支払うことで、被害者に対する民事上の責任を果たし、謝罪や反省を示したとして不起訴処分と判断される場合があります。また、賠償金の支払いによって被害者の処罰感情が和らぎ、告訴の取り下げにつながる可能性もあるでしょう。
-
(3)反省文や謝罪文を作成する
心から反省していることを示す方法として、反省文や謝罪文を作成する手段もあります。反省文は検察庁、謝罪文は被害者に渡すために作成します。
反省文・謝罪文には、事件を起こした経緯や理由・被害者への謝罪・更生に向けた決意などを真摯に記載しましょう。
これにより、検察官が「十分に反省しており、再犯の可能性が低い」と判断し、不起訴となる場合があります。 -
(4)被害者に告訴を取り消してもらう
親告罪であれば、被害者に告訴を取り消してもらうことが特に重要となります。侮辱罪・名誉毀損罪・器物損壊罪などの犯罪は、検察官が公訴を起こす際に被害者側の告訴が必要となる親告罪です。
そのため、起訴される前に被害者に告訴を取り下げてもらえれば、原則として起訴されません。
ただし、告訴の取り下げは被害者の意思によるものであり、強要や圧力をかける行為は逆効果になるため注意しましょう。 -
(5)弁護士に相談する
不起訴を目指すためには、早めに弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は、被害者との示談交渉の代行・検察官に対する意見書の提出など、被疑者の立場を有利にするための活動を行えます。
逮捕された後、起訴・不起訴が判断されるまでの期間は最大で23日間です。
できるだけ早い段階で相談することによって、どのように不起訴を目指すべきか適切なアドバイスが得られるでしょう。
4、逮捕後のサポートは弁護士に相談を
家族が逮捕された際、どのように対応すればいいのかわからず不安を感じたときには、弁護士に相談することをおすすめします。以下では、弁護士に相談するメリットについて具体的に解説していきます。
-
(1)不起訴を獲得するためのサポートができる
弁護士は、不起訴処分を獲得するためのサポートができます。起訴を避けるには、検察官に対して被疑者の反省や事件の重大性の低さ、被害者との示談成立などを示すことが重要です。
しかし、被疑者やその家族が具体的になにをすべきか、すぐに適切な判断をするのは難しいケースもあるでしょう。弁護士であれば、検察官に対する主張や被害者との交渉・被疑者へのアドバイスなど、具体的な弁護活動が可能です。
法律知識をもつ弁護士が早期に対応することで、不起訴処分となる可能性を高められるでしょう。 -
(2)早期釈放の可能性が高まる
弁護士に相談することで、早期に釈放される可能性を高められるメリットもあります。
逮捕された後、勾留されると最大23日間身柄を拘束されます。そのため、早期釈放を目指すためには勾留を回避することが重要です。
弁護士は勾留の要件を欠いていることを主張したり、釈放を求める意見書を提出したりして勾留の阻止をサポートできます。手続きを迅速に進めるためにも、できるだけ早い段階で弁護士への相談を検討しましょう。 -
(3)被害者との示談交渉ができる
不起訴処分を得るためには、被害者との示談交渉が大きなポイントになります。
しかし、加害者本人や家族が直接交渉することは難しく、かえって相手を刺激してしまうリスクもあります。また、加害者側から被害者に連絡を取りたいと思っても、警察や検察から連絡先を入手できない場合も多いでしょう。
弁護士が介入することで、被疑者本人が申し出るよりもスムーズに被害者と連絡がつく可能性があります。冷静かつ法的に適切な形で交渉を進めるためにも、被害者との示談交渉は弁護士に任せた方が得策です。
5、まとめ
刑事事件の起訴・不起訴を決めるのは、検察官です。検察官は証拠や被疑者の状況を総合的に判断し、裁判にかけるべきかどうかを決定します。
不起訴処分となった場合、前歴は残るものの前科はつきません。
逮捕後に不起訴を目指すためには、被害者との示談成立や告訴を取り消してもらうことが重要です。しかし、示談交渉には被害者の感情や法的な手続きが関わるため、被疑者本人や家族が直接行うのは難しいケースも多いでしょう。
そのため、不起訴処分を目指すためには早めに法的知識のある弁護士に依頼することをおすすめします。身近な方が逮捕されてしまい悩んでいるときは、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています