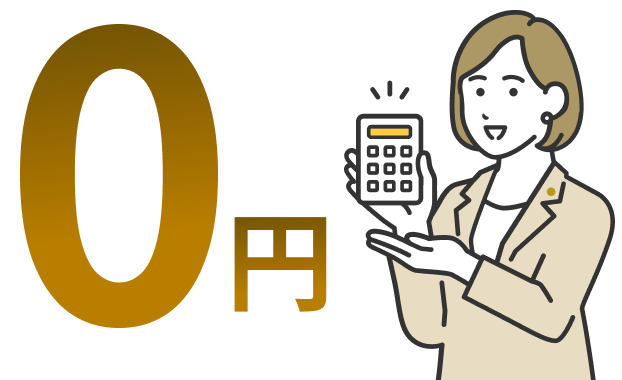推定相続人とは? 法定相続人との違いなど相続人のルールについて弁護士が解説
- 遺産を受け取る方
- 推定相続人とは

相続では、故人が生前に行った贈与や親族による遺産の使い込みが発端となって、親族間でトラブルが生じることも少なくありません。
令和元年の統計では、熊本家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の紛争件数は年間約240件にまでのぼっているのです。(出典:最高裁判所司法統計)
民法では、相続が始まる前の段階について、「推定相続人」に関する規定が設けられています。
推定相続人に関する知識は、相続のトラブルを未然に防ぐうえで重要です。
本コラムでは、「推定相続人」という言葉の意味から、推定相続人に関する法律の詳細まで、べリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士が解説いたします。
1、「推定相続人」とは? 誰がなるのか?
「推定相続人」とはどのような存在であるか、どのような人が推定相続人になるのかという点について、解説いたします。
-
(1)推定相続人とは何か
民法では、推定相続人について、「相続が開始した場合に相続人となるべき者」と規定されています(民法892条)。
「相続が開始した場合」とは被相続人(相続財産を遺す方)が亡くなった場合を指します(民法882条)。
また、「相続人となるべき者」とは、民法の規定により定まる「法定相続人」のことを意味するのです。
つまり、推定相続人とは、「被相続人が亡くなったと仮定した場合に、その時点で法定相続人の立場にある方」ということになるのです。 -
(2)推定相続人となる親族
推定相続人と法定相続人を決定するルールは共通しており、被相続人との親族関係によって決定されます。
法定相続人となるのは、「配偶者」と、「血族相続人」と呼ばれる親族に限られます(民法887条、889条、890条)。
①配偶者
法律的に「配偶者」と見なされるためには、法律上の婚姻関係にあることが要件となります。
内縁関係や離婚した元配偶者では、法定相続人になることはできません。
一方で、配偶者は常に法定相続人となり、血族相続人のいずれかとともに遺産を分け合うことになるのです。
②血族相続人
血族とは、血縁関係のある親や子、きょうだいのことです。また、養子縁組による法律上の親子関係も、「血族」に含まれます。
そして、血族のなかでも、以下の優先順位で最も上位の者が法定相続人となるのです。
●直系卑属(第1順位)
「直系」とは親子の系統のことをいい、「卑属」とは下の世代のことを指します。
基本的に、法定相続人となる直系卑属は。被相続人の「子」です。
しかし、「子」が被相続人より先に亡くなっている場合には、孫やひ孫が代襲して相続することになります。
財産の相続分については、配偶者が2分の1、直系卑属が残りを均等に分け合います。
●直系尊属(第2順位)
「尊属」とは上の世代のことを指します。
法定相続人となる直系尊属は、被相続人の「親」や「祖父母」です。
母親と父方の祖母など、世代が異なる尊属がいる場合には、最も世代が近い人が法定相続人となります。
相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が残りを均等に分け合うことになるのです。
●きょうだい(第3順位)
父母が共通のきょうだいと一方のみが共通するきょうだいは、いずれもが法定相続人となります。
また、きょうだいが先に亡くなっている場合、きょうだいの子の世代までが「代襲者」として法定相続人になるのです。
相続分は、配偶者が2分の3、きょうだいが残りを均等に分け合います。
ただし、きょうだい間では、父母の一方のみが共通するきょうだいの相続分は2分の1となります。
2、推定相続人、法定相続人、相続人の違い
相続人としての立場の推移を時系列でまとめると、次のようになります。
- ①生前の親族関係で推定相続人が特定される
- ②相続開始時の親族関係で法定相続人が確定する
- ③相続放棄の有無、遺言、遺産分割協議などにより具体的な相続分が決まる
それぞれの段階で法的な立場や権利の内容の違いについて、解説いたします。
-
(1)推定相続人の権利は「期待権」
推定相続人には、被相続人が保有する相続財産について、具体的な権利といえるものはなにもありません。
被相続人が存命中は、自己の財産の管理や処分は本人が自由に行うことができます。原則として、推定相続人といえども、それに干渉することはできないのです。
推定相続人の権利の内容が問題になった過去の民事事件では、被相続人が所有する不動産を他人に売却したことに関して、推定相続人が相続権に基づいてその無効を主張したのに対し、最高裁判所は次のように判断して推定相続人の主張を退けました。
「推定相続人は、単に、将来相続開始の際、被相続人の権利義務を包括的に承継すべき期待権を有するだけであって、現在においては、未だ当然には、被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではない。」
つまり、「推定相続人の権利は、将来相続を受けることを期待する権利にとどまる」ということです。
ただし、推定相続人が被相続人から贈与を受けるなどの利益を得た場合には、遺産分割では「特別受益」として考慮される可能性があります。
しかし、その贈与自体を差し止めるような権利はないのです。
なお、被相続人が認知症などで財産の管理がままならなくなった場合には、成年後見制度を利用して財産の散逸を防ぐことを検討する必要があるでしょう。 -
(2)法定相続人に保障される権利は「遺留分」
相続が開始して法定相続人となっても、法定相続分に応じた財産を必ず相続できるわけではありません。被相続人の遺言で、法定相続分とは異なる遺産の分配が定められていたり、相続人以外の人に遺産を渡す旨定められている場合があるからです。
法定相続人の段階で認められるのは、「遺留分」という権利です。
相続には、遺族の生活を保障するという側面があるため、一部の法定相続人には、最低限の相続財産を受け取る権利(遺留分)が保障されています。
遺留分がある法定相続人は配偶者と直系卑属と直系尊属のみで、きょうだいには遺留分がありません。
なお、遺留分の割合は、法定相続人各自の法定相続分に、被相続人の直系尊属のみが相続人である場合は「3分の1」、その他の場合は「2分の1」を乗じたものとなります(民法1042条)。
遺留分は被相続人の遺言でも制限することはできないため、きょうだい以外の法定相続人は、遺留分に関しては権利として主張できることになるのです。
3、相続人となるまで
親族関係に変動がなければ、推定相続人は相続開始によって「法定相続人」となり、やがて「相続人」になります。
法定相続人が実際に相続財産を引き継ぐまでの手順について、解説いたします。
-
(1)遺言で指定される場合
誰にどれだけの財産を相続させるのかは、被相続人が自由に決めることができます。
そのため、遺言書がある場合には、その内容にしたがって相続人と相続分が決まることになるのです。
なお、推定相続人は、遺言書の作成手続には一切関与することができません(民法974条2号)。また、詐欺や強迫などの手段で被相続人の遺言書作成や変更を妨害した場合には、推定相続人から除外されてしまうこともあるのです。 -
(2)遺産分割協議により決める場合
遺言がない場合には、具体的な相続分は法定相続人で協議したうえで、全員の合意で決める必要があります。
遺産分割協議においては、法定相続分は「一応の目安」として参考にされます。
また、被相続人から生前に受けた贈与がある場合には、「特別受益」として相続財産に持ち戻され、相続分から差し引かれる可能性もあるのです。 -
(3)相続人とならないケース
推定相続人や法定相続人が相続人とはならないケースも存在します。
①相続放棄をした場合
相続放棄をすると、「相続人ではない」ということになり、被相続人の権利や義務の一切を受け継がないことになります。
被相続人が財産よりも負債の方を多く抱えているような場合には、相続放棄をすることが一般的です。
相続放棄は、相続の開始を知った時点から3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります(民法915条)。
②被相続人が遺言で子を認知した場合
子の認知は遺言によってすることもでき(民法781条)、親の死後3年間は子の側から認知の訴えが起こされることもあります(民法787条)。
認知された子は第1順位の血族相続人となり、相続関係が変動する可能性もあるのです。
③相続人になる可能性がある胎児がいる場合
遺産相続においては、まだお腹のなかにいる胎児であっても、すでに生まれたものとみなされることになっています。ただし、死産となった場合には、その限りではありません(民法886条)。
つまり、相続人になる可能性がある胎児がいる場合は、出産の結果によって相続関係が変動する可能性があるのです。
④相続欠格事由がある場合
推定相続人が相続に関して利益を得る目的で次のような行為した場合には、相続権が剥奪されることになります(民法891条)。
●被相続人や他の相続人に対する殺人(未遂)罪などで刑に処せられた場合
この場合は、故意に死亡させようとした罪に限られます。運転操作を誤って発生した交通事故により死亡させたような事例は、該当しないのです。
また、刑事裁判によって刑に処せられることが要件ですので、その疑いがあるというだけでは欠格事由とはなりません。
●被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合
被相続人を殺害した犯人をかばおうとして告訴や告発をしなかった際にも、相続欠格事由となります。
ただし、犯人の配偶者や直系血族(親子の血統)、告訴や告発を行うことができない子どもである場合には、相続の欠格が免除されます。
●詐欺や強迫の手段により、遺言の内容に干渉した場合
被相続人が行う遺言の作成や変更、取り消しに関して、詐欺や強迫により妨害した場合には相続欠格事由となります。
また、遺言書の偽造や変造、破棄、隠匿する行為も相続欠格事由となるのです。
4、相続させたくない推定相続人がいる場合
非行が目に余る推定相続人がいる場合には、被相続人の意思によって推定相続人の相続権を剥奪できる制度があります。
これを、推定相続人の「廃除」といいます。
遺言により特定の推定相続人に遺産を相続させないことにしても、きょうだい以外の法定相続人には遺留分を主張されてしまいます。
その遺留分すら相続させたくないという場合には、廃除をするほかありません。
-
(1)廃除が認められる理由とは
民法では、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求できることとされています(民法892条)。
「著しい非行」は、被相続人に対する言動に限られません。
廃除が認められる目安としては、「家族間の共同生活を破壊する程度」、または「離婚や離縁が認められる程度」の言動であることが必要とされています。
暴力や暴言以外の具体例としては、以下のようなものがあります。- ギャンブルなどによる借金を肩代わりさせた
- 重大な犯罪により服役した
- 反社会的勢力の構成員と結婚した
- 介護や扶養をしなかった
- 財産の着服
- 家庭を顧みない不貞行為
-
(2)廃除の方法
生前に推定相続人を廃除する場合は、被相続人が家庭裁判所に廃除を申し立てる必要があります。
また、遺言により廃除をすることもできます。その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをします(民法893条)。
また、廃除の取り消しも、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
令和元年に全国の家庭裁判所で扱われた推定相続人の廃除と廃除の取り消しの処理状況は次のようになっています。(出典:最高裁判所司法統計)- 申し立て……197件
- 申し立てを認める審判……30件
- 申し立てを却下する審判……101件
- 申し立ての取り下げ……66件
ここ数年間、廃除に関する申し立てが認められる割合は2割前後で推移しており、廃除が認められるためのハードルはかなり高くなっているといえるでしょう。
-
(3)廃除の効果
廃除の効果は、欠格の場合と同様に、廃除された人にのみ及びます。
また、廃除を認める審判が確定した場合、廃除された推定相続人の戸籍に「推定相続人廃除」の記載をする必要があるため、市役所などに届け出を行う必要があります。
5、まとめ
遺産相続においては、推定相続人のほかにも「遺留分」や「廃除」など、相続に独自の複雑な専門用語が関わってきます。
ベリーベスト法律事務所では、相続問題のサポート経験が豊富な弁護士に加えて、グループ傘下に税理士や司法書士が所属しています。幅広い相続のお悩みに対応することが可能です。
将来の相続について不安があるという方は、ぜひ、べリーベスト法律事務所 熊本オフィスにまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています