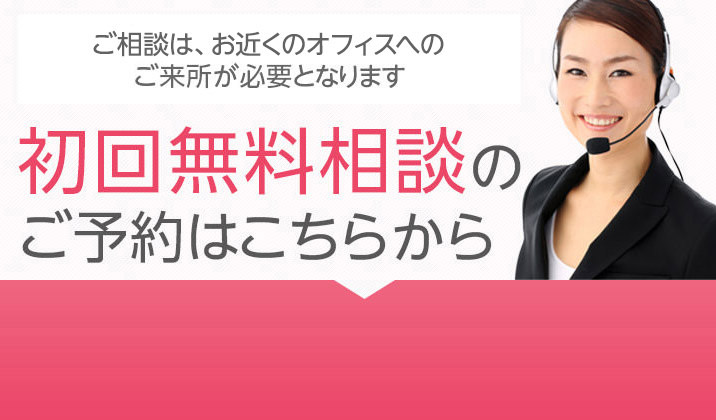離婚届を偽造で提出するとどうなる? 違法性やリスクを弁護士が解説
- 離婚
- 離婚届
- 偽造

熊本県が公表している人口動態調査によると、令和4年の熊本県の離婚件数は2,482組で、前年より195組減少しました。
離婚は、基本的に夫婦の同意により行う手続きですが、配偶者が同意しないことを理由に、勝手に手続きを進めたいとお考えの方もいるかもしれません。しかし、離婚届を偽造して役場に提出することで、何かしらのペナルティーを負うかもしれないと、不安な方もいるでしょう。
本コラムでは、離婚届を偽造するリスクや、離婚に同意してくれない配偶者への対処法について、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士が解説していきます。


1、離婚届を偽造して提出することは違法?
離婚手続きを進めるため、偽造した離婚届を役場に届けると、法的リスクが生じます。詳しく解説しましょう。
-
(1)離婚届偽造・提出の違法性
そもそも、夫婦で話し合って離婚する「協議離婚」の成立には、双方の離婚意思(離婚をする意思)があることが欠かせません。そのため、配偶者の意思を無視して離婚届を偽造し、提出する行為は、違法行為にあたります。さらに、悪質な場合は、刑事罰を受ける可能性もあります。
具体的には、役所に提出するために離婚届を偽造する行為が、刑法159条1項の「有印私文書偽造罪」に該当します。法定刑は、3カ月以上または5年以下の拘禁刑です。
さらに、偽造した離婚届を実際に役所へ提出すると、刑法161条の「偽造有印私文書行使罪」に該当します。この場合の法定刑も、3カ月以上または5年以下の拘禁刑です。
また、これらの行為は、公務員に対して虚偽の申し立てをし、戸籍に虚偽の記載をさせたことになります。この場合、刑法157条1項の「公正証書原本不実記載等罪」に該当し、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
さらに、勝手に離婚届を提出したことで、配偶者から損害賠償を請求されるリスクもあるでしょう。 -
(2)偽造離婚届の提出後に再婚する場合のリスク
偽造した離婚届を提出してから再婚をすると、刑法184条の「重婚罪」に該当し、2年以下の拘禁刑になる可能性があります。
偽造した離婚届は無効であるため、役所で受理されても、法的には配偶者との婚姻関係が続いていることに変わりありません。そのため、再婚したつもりでも、実際は複数人と同時に婚姻をしている「重婚」になってしまいます。
2、離婚届を偽造して提出したあとはどうなる?
勝手に離婚届を提出してしまった場合、今後どのようなことが起こるのか紹介しましょう。
-
(1)相手に離婚届受理通知が送付される
離婚届は、夫婦揃ってではなく、ひとりでも市町村役場に提出可能です。しかし、ひとりで提出する場合は、配偶者に後日「離婚届受理通知」が送付されます。離婚届受理通知を受け取ることで、配偶者は離婚届が受理されたことを確認できる仕組みです。
仮に、妻が勝手に離婚届を提出したとすると、夫が住民登録をしている住所に受理通知が送られます。夫が通知を受け取れば、妻が離婚届を提出したことはバレてしまうでしょう。 -
(2)協議離婚無効確認調停が申し立てられる
先述のとおり、離婚の成立には双方の離婚意思が欠かせないため、一方が勝手に偽造して提出した離婚届は無効です。しかし、役場ではその場で偽造に気づかれずに受理され、戸籍に離婚したことが記載されてしまうこともあるでしょう。その情報を削除するために、配偶者から「協議離婚無効確認調停」を申し立てられる可能性があります。
調停は、調停委員の仲介のもとで話し合い、トラブルを解決する制度です。調停で協議離婚が無効であると双方が合意すると、家庭裁判所が必要な事実調査などを行います。そのうえで、「協議離婚無効の合意は正当である」と認められれば、合意に相当する審判がなされ、市町村役場に戸籍訂正の申請を行います。
しかし、離婚は成立していると主張するなどして調停が不成立になると、「協議離婚無効確認訴訟」を提起される可能性があります。訴訟では、勝手に離婚届を出したことに対して、無効か否かの最終的な判断が裁判官から下されることになるでしょう。
お問い合わせください。
3、離婚に合意してくれない配偶者への対処法
ここまで解説してきたように、偽造した離婚届を提出することは違法行為です。勝手に提出しても、調停や訴訟で後日離婚が無効になる可能性があります。
また、配偶者が離婚に合意してくれないからといって、離婚届への署名の強要はしてはいけません。離婚届への署名の強要は、刑事罰(強要罪や脅迫罪)に該当するおそれがあるからです。
離婚したくても配偶者に拒否をされてしまう場合には、どのようにして離婚への合意を目指すべきか悩む方もいるでしょう。以下で、対処法を紹介します。
-
(1)親や知人に相談する
離婚について配偶者と話し合うだけではなく、親や知人に相談することも検討しましょう。自分や配偶者の性格を理解した方であれば、どうすれば離婚に合意してもらえるか、客観的なアドバイスを受けられる可能性があります。
ただし、配偶者と相談せず、いきなり親や知人が仲介に入ろうとすると、かえってこじれるリスクもあります。また、仲介に入った方が、配偶者を必要以上に責めてしまうこともあるかもしれません。
したがって、どなたに相談するかどうかは、慎重に決めるようにしましょう。双方が冷静に話し合えるように仲介してもらいたい場合は、離婚カウンセラーや弁護士などへの依頼も検討してみてください。 -
(2)別居から提案する
離婚に合意してもらえない場合、まずは別居で距離を置くことから提案する方法もあります。同居している間は、配偶者と顔を合わせることで喧嘩になってしまうことが多いかもしれません。しかし、お互いに会う機会が減ると、冷静に離婚について考えられるようになることもあるでしょう。
また、配偶者が離婚に合意しないことを理由として、今後離婚調停や離婚裁判を検討する可能性がある方は、別の理由で別居をするメリットがあります。別居期間が長くなると、法定離婚事由(法律上離婚が認められる離婚原因)に該当するとして、離婚裁判で離婚が認められる可能性があります。
したがって、離婚を拒否されている場合は、別居から提案してみることも検討しましょう。 -
(3)相手が有責配偶者の場合、証拠を集めて離婚を切り出す
配偶者の不倫やDVを理由に離婚をしたい場合、証拠を集めて言い逃れができないようにしてから離婚を切り出すことで、離婚に合意してもらえる可能性があります。
離婚原因を作った配偶者は「有責配偶者」と呼ばれます。有責行為の証拠があれば、有責配偶者がごねて裁判に発展したとしても、離婚は認められやすくなるでしょう。
証拠の例として、不倫の場合は不倫相手との肉体関係がわかる写真・動画や、興信所の調査書などがあります。DVの場合は、配偶者によって受けたケガの写真や、ケガの診断書が証拠となりえるでしょう。相手の非を決定的にする証拠を確保しておくことで、配偶者が誠実に離婚の話し合いに応じる可能性が高まるかもしれません。 -
(4)弁護士に相談する
離婚問題は、当事者同士での話し合いはもちろん、親や知人に仲介してもらっても、感情的になって時間がかかるリスクがあります。冷静にスムーズに離婚手続きを行うには、弁護士に相談するのがおすすめです。
4、離婚についてのトラブルを弁護士に相談するメリット
相手が離婚に合意してくれない、離婚条件で揉めているといったトラブルでお悩みの場合、ひとりで抱え込まず、弁護士に相談しましょう。
配偶者との交渉を弁護士に任せることで、離婚への合意を得られやすくなります。さらに、財産分与、親権、慰謝料などの離婚条件について合理的な内容で決められる可能性が高まるといえます。
なお、話し合いがまとまらず、調停や裁判に進むことになっても、引き続き交渉の対応ができます。また、裁判所への手続きや、離婚を認めてもらうための法的アドバイスなどをサポート可能です。
離婚の話し合いは、精神的な負荷も大きくなるでしょう。話し合いを弁護士に依頼することで、ストレスを軽減しながら、離婚手続きを進められます。
そのため、離婚についてお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
5、まとめ
離婚届を偽造して提出することは、「有印私文書偽造罪」や「偽造有印私文書行使罪」といった犯罪行為に該当します。裁判で刑事罰を受けるおそれがあるだけではなく、損害賠償請求をされるリスクもあるため、絶対にやらないようにしましょう。
配偶者がなかなか離婚に応じてくれない場合は、弁護士への依頼をご検討ください。弁護士であれば、配偶者との交渉を代行でき、条件面を有利に進められる可能性が高まります。もし離婚調停や離婚裁判に進んだとしても、引き続き交渉を代行できるうえに、法的な手続きにも対応できます。
「早く離婚がしたい」「少しでも有利に離婚したい」といったお悩みがある方は、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています