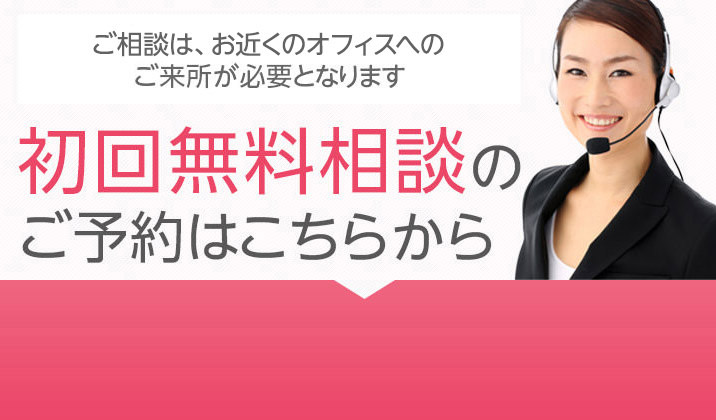主な離婚方法は3種類|離婚の流れと離婚時の取り決め事項を解説
- 離婚
- 離婚
- 方法
- 種類

熊本市では、令和4年(2022年)より「離婚届」の原本を、市のホームページからダウンロードできるようになっています。ダウンロードしたものを印刷して必要事項を入力すれば、届け出に使用することが可能です。
離婚届を提出すれば、離婚は成立します。ただし、離婚届を提出するためには、夫婦間で離婚および離婚条件に合意しなければいけません。離婚を成立させる方法は主に3種類あり、その流れもそれぞれ異なります。
この記事では、離婚の方法・種類や流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。


1、離婚するための主な方法は3種類
離婚の方法は大きく分類すると3種類です。まずはそれぞれの内容について解説します。
-
(1)協議離婚
夫婦が離婚する方法として、もっとも一般的なのが「協議離婚」です。
民法には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と規定されています(民法第763条)。
つまり、夫婦が話し合いを行い、合意すれば離婚を成立できるということです。双方が離婚条件に納得して行う離婚方法であるため、どのような離婚原因であっても離婚することは認められます。 -
(2)調停離婚(審判離婚)
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きを利用する離婚方法です。
当事者間の話し合いでは離婚の合意に至らなかった場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合などに選択します。
調停手続きは、裁判のように当事者の言い分が正しいかどうかを決めるものではなく、家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入って話し合いを進めていき、離婚成立を目指す手続きです。調停手続きでも合意に至らなかった場合には、調停は不成立(不調)となります。
なお、双方離婚には合意できているものの、ささいな離婚条件について意見の相違がある場合や、それぞれ離婚と離婚条件には合意しているものの調停期日に出席できない事情がある場合などには、裁判官が一切の事情を考慮して調停に代わる審判をすることができます。このように、家庭裁判所の審判に従い離婚する方法を「審判離婚」といいます。
ただし、裁判官の審判に不服がある当事者は、審判から2週間以内であれば異議申し立てを行うことができます。 -
(3)裁判離婚
調停が不調に終わった場合には、「裁判離婚」を提起し、離婚を求めることになります。裁判離婚とは、裁判所に訴訟を提起して、裁判所に離婚の可否を判断してもらう手続きです。
ただし、裁判離婚をするためには、民法に規定された特定の離婚原因に該当している必要があります。このような離婚原因を法定離婚事由といいます。
法定離婚事由として規定されているのは、5つの離婚原因です(民法第770条1項)。- ① 配偶者に不貞な行為があったとき
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
-
(4)その他(和解離婚・認諾離婚)
その他の離婚方法として、「和解離婚」と「認諾離婚」がありますが、これらはいずれも裁判離婚内の手続きのため、裁判離婚に含めて考えることができます。
まず、「和解離婚」とは、裁判離婚の手続きにおいて、訴訟係属中に裁判上の和解によって離婚を成立させることをいいます。
これに対して「認諾離婚」とは、被告が原告の離婚請求を全面的に受け入れて離婚することを指します。
ただし、認諾離婚ができるのは、原告が被告に対して離婚のみを求めている場合です。離婚以外に親権・養育費・財産分与など離婚に付随する問題を訴えに含めている場合には、たとえ被告が請求を認めていたとしても認諾離婚はできません(人事訴訟法第37条1項但書)。
2、【種類別に解説】離婚の流れとは
離婚の種類ごとに、離婚までの流れは異なります。それぞれ確認していきましょう。
-
(1)協議離婚の流れ
協議離婚は、離婚を切り出すことからスタートします。その後、離婚の状況を話し合い、離婚協議書を作成します。すべてが完了した後、離婚届を役所に提出します。
具体的な進め方とポイントを工程ごとに説明します。・配偶者に離婚を切り出す
離婚を決意した場合、口頭やメールなどで相手に対して離婚したい旨を伝えましょう。離婚成立までには話し合うべきこと、決めるべきことが多岐にわたります。感情的にならず冷静に伝えることが大切です。
・夫婦間で離婚条件を話し合う
離婚してから紛争が起こらないように、離婚条件についてはしっかりと夫婦で話し合う必要があります。
・合意した内容で離婚協議書を作成する
話し合いで取り決めを行った事項については、必ず離婚協議書を作成し記録として残しましょう。当事者間の合意を書面という客観的な形で残しておくことで、後になって「約束した・していない」というトラブルを予防することにもつながります。
なお、養育費などといった債権債務の内容を含む場合は、支払いトラブルが生じた際に速やかに強制執行することができるよう、公正証書で作成しておくことをおすすめします。
・離婚届を役所に提出する
離婚届を「夫婦の本籍地」または「夫または妻の住民票上の住所地」、いずれかの役所に提出します。届け出の際には、夫婦の戸籍謄本や本人確認書類が必要となることがありますので、事前に役所に問い合わせをして確認しておきましょう。 -
(2)調停離婚・審判離婚の流れ
裁判所に、離婚調停を申し立て立てたることからスタートします。
・離婚調停を申し立てる
夫婦のうち離婚を希望する側が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てを行います。調停を申し立てるためには、「申立書とその写し」、「夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)」を持参または郵送で提出が必要です。
・調停期日に話し合いを行う
調停が適切に申し立てられた場合には、期日が指定され当事者に呼出状が届きます。
1回の期日は2時間程度で、およそ30分ずつ、調停委員が夫婦交互に事情を聴取する形式です。基本的には月に1回期日が設定され、複数回の調停期日を経たうえで合意に至る道を探ることになります。
・調停成立/不成立
調停の結果、合意できた場合には調停が成立し、調停調書が作成されます。調停が成立してから10日以内に、離婚届と調停調書謄本を役所に提出しましょう。
合意できなかった場合には、調停は不成立となり終了します。
・調停に代わる審判
調停が不成立となり裁判所が必要と判断した場合には、調停に代わる審判が行われます。
審判が確定した場合は、審判の内容が記載された審判書が作成されます。審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に異議申し立てがなされなければ、審判は確定です。
審判が確定してから10日以内に、審判確定証明書を裁判所から受け取り、離婚届と審判書の謄本とともに役所に提出することで離婚が成立します。休日も含めて10日以内に提出する必要があるので提出期間には十分気を付けましょう。 -
(3)裁判離婚の流れ
裁判により離婚を求める場合には、訴状や答弁書の作成が必要になるため、弁護士のサポートを受けた方がいいケースが多いでしょう。
・訴状の提出
離婚を希望する当事者が、管轄の家庭裁判所に訴状を提出します。訴状には、法定離婚事由に該当すること、離婚を請求することのほか、養育費や財産分与など請求したい事柄の記載が必要です。
・期日指定・答弁書の提出
訴状が適法と判断された場合には、第1回口頭弁論期日が指定され、それまでに被告は答弁書を提出することになります。
・口頭弁論、証拠調べの実施
月1回のペースで指定される弁論期日に、双方ともに主張と立証を尽くしながら、争点を明確にしていきます。判決は、本人尋問が実施され、裁判官による和解勧告の後に言い渡されることが一般的です。
・判決・和解による訴訟終了
訴訟上の和解が成立した場合、訴訟は終了です。
和解が成立しない場合には、裁判所が判決によって離婚請求の可否や離婚条件に関する判断を行います。
和解または判決が確定したら、10日以内に判決謄本と確定証明書を添えて離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
3、離婚前に取り決めておきたいこと
離婚届を提出することで離婚は成立しますが、離婚条件をしっかりと決めておかなければ、後悔することにもなりかねません。最低限、押さえておきたい取り決めを把握しておきましょう。
-
(1)財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持した共有財産については、離婚時に財産分与請求をすることができます(民法第768条1項)。
共有財産については、2分の1ずつの割合で分与するのが原則です。 -
(2)年金分割
婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割することを、年金分割といいます。
年金分割手続きが行われると、厚生年金の支給額を計算するときの元になる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになります。 -
(3)親権・養育費・面会交流
未成年の子どもがいる場合、父母のいずれかを親権者と指定します。そして、親権者は非監護親に対して月々の養育費の支払いを請求することができます。
また、子どもと非監護親との面会交流の実施方法についても、離婚の際に取り決めておくべきでしょう。 -
(4)慰謝料
離婚に至る直接的な原因に不法行為があった場合は、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額を考慮したうえで、前述の財産分与の取り決めを行うこともあります。
4、離婚の進め方を弁護士に相談するメリット
離婚問題は、第三者に相談しにくい事柄です。お金や子どものことが絡むため、複雑化することも少なくありません。そのため、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)代理で交渉してもらえる
弁護士は、相手との話し合いや交渉を代理することができます。
関係がこじれている配偶者と直接顔を合わさずに手続きを進めることができるので、心身の負担は大幅に軽減されるでしょう。また、しっかりと希望を伝えつつも、冷静に交渉を進めることができます。 -
(2)適切な離婚の進め方についてアドバイスを受けられる
夫婦の関係性、抱えている問題、結婚年数などが複雑に絡み合うため、離婚の適切な進め方は、状況によって異なります。弁護士であれば、状況に適したアドバイスを行うことが可能です。適切な進め方がわかれば、離婚成立まで最短の道筋を選択することができるでしょう。
-
(3)手続きを代行してくれる
調停や訴訟に至った際、弁護士は本人の代理人として、裁判対応や書面提出などを代行することが可能です。
慣れない手続きを任せられるだけではなく、離婚条件の漏れや不利な内容を見落とすという余計な心配ごとも減らせます。
お問い合わせください。
5、まとめ
離婚をする主なる方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
協議離婚からスタートするのが一般的ではありますが、個別のケースによって最適な離婚の進め方は異なります。離婚の進め方に不安がある方や、条件の取り決めに失敗したくないという方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスには、離婚事件の解決実績の豊富な弁護士が在籍しております。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています