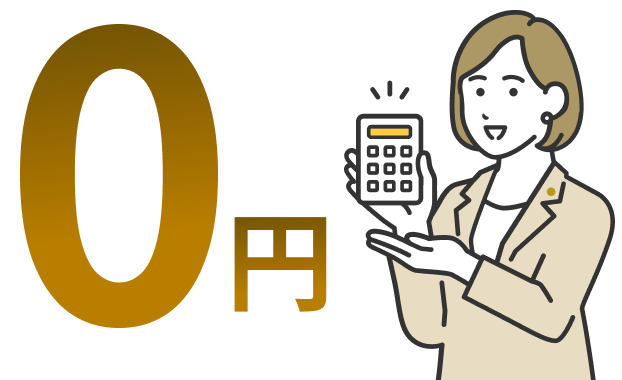遺言能力とは? 遺言者に認知症の疑いがある場合の対処法を解説
- 遺言
- 遺言能力
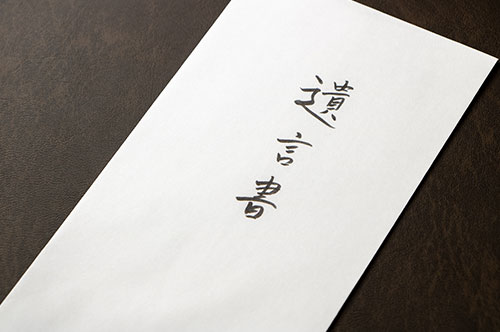
熊本市の認知症を患う高齢者数は、2025年には約4万人になることが推計されています。
認知症と相続問題とは、密接に関係しています。たとえば認知症を理由に、親が残してくれた遺言について、きょうだいやその配偶者があとから文句を言ってくる、ということがあるのです。
親が認知症であった場合には、遺言能力を否定される結果、遺言そのものが無効になってしまう可能性があります。また、遺言が公正証書遺言であった場合でも、無効と判断されるケースがあるため、油断はできません。
本コラムでは、遺言能力の判断基準や実際の争い方について、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士が解説します。
1、遺言能力とは?
-
(1)遺言ができるのは誰か
法律上、有効に遺言を作成できる人の要件は、下記のようになっています。
- ① 満15歳以上の者(民法961条)
- ② 遺言能力がある者(民法963条)
遺言は、代理で行うことができません(遺言代理の禁止)。
また、遺言には、未成年者等の行為能力制度の適用がなく(民法962条)、遺言者の意思が尊重される制度になっています。
そのうえで、民法は、遺言に関する年齢制限について15歳以上であれば有効に遺言ができるものと規定しています。言い換えれば、15歳未満であれば、親の同意があっても有効な遺言はできません。
一方で、15歳になれば、親がどんなに反対しても自分一人で有効に遺言ができるということです。
しかし、何歳であっても、遺言能力が認められなければその遺言は無効となってしまうのです。 -
(2)遺言能力とは
遺言能力とは、「自分の遺言の内容を理解し、遺言によって起こる結果を認識できる判断能力のこと」をいいます。
具体的に説明すると、遺言をする時に、「自分がのこす遺言の意味や内容を理解できる」「その遺言によって、だれにどんな効果が生じるのかを理解できる」状態でなければ、その遺言は有効なものにはならない、ということです。
遺言を作成したとしても、何らかの理由で遺言能力が無いと判断されると、せっかく作成した遺言が無効になってしまうので注意しましょう。 -
(3)成年被後見人の遺言
認知症状が進み、事理弁識能力が著しく衰えた方は、自分の財産を管理することができなくなっていきます。このような場合に、本人を支えるシステムとして利用されるのが「成年後見人」の制度です。
裁判所に後見人選任の審判がなされると、本人ではなく成年後見人によって財産の管理が行われることになります。
原則として、ある人が成年後見人を付けられる「成年被後見人」になると、その人は自分の財産を管理する能力がないということなので、遺言能力も認められない事になる、と考えられるでしょう。
ところが、遺言については、以下のような特別な規定があるのです。(成年被後見人の遺言)
第973条
1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
高齢者の方は、普段はなかなか話が会話できないが、場合によって通常どおりに会話がすることができる、という状態の方がおられます。
認知症が進んでも一時的に意思能力が回復することはあり得るため、成年被後見人となられた方であっても、場合によっては、意識がはっきりしているタイミングもあります。
そこで、一時的に意思が回復しているということを、2名以上の医師が立ち会い、その医師による証明を受けた場合には、成年被後見人であっても、自分の意思で遺言を有効に残すことができるのです。
ただし、立ち会ってくれる医師を見つけることが難しいなどの問題から、実務上は、この制度はなかなか利用されていないという現状があります。 -
(4)遺言能力が無いとどうなるか
遺言能力が無い状態で書かれた遺言は、「無効」となります。
たとえ公正証書遺言であったり、きれいに書かれた自筆遺言であったりしたとしても、「その遺言が書かれた時に、遺言能力があったといえるか」が遺言の効力を決定するのです。
ここで、「遺言作成時に本人に遺言能力があったかどうか」を、いったいどうやって判断するか、ということが問題になります。
遺言の有効無効の判断は、遺言を作った本人が死亡したあとでなければ、法的に争うことができません。つまり、遺言の有効性が問題となる時には、その遺言を書いた遺言者は既に死亡しているのです。
したがって、本人に遺言当時の様子をたずねることもできず、ただ残された資料を基礎として、事後的かつ客観的に判断するしかない、ということになります。
2、遺言能力の判断基準
-
(1)遺言無効確認の訴え
遺言能力の有無は、最終的には、裁判で争われることになります。
裁判官は、当事者から提出されたさまざまな証拠を照らし合わせることで、「遺言当時に遺言者が遺言能力を持っていたかどうか」「その遺言が有効かどうか」を決めます。
この裁判のことを「遺言無効確認の訴え」といいます。
遺言無効確認の訴えで遺言能力の有無について裁判所が総合的な判断を下す際に考慮される要素としては、以下のようなものがあります。 -
(2)遺言能力を判断する際の主な考慮要素
① 遺言者の年齢
遺言者の年齢は重要な要素です。
たとえば、40歳と99歳とを比較すれば、99歳の人物のほうが判断能力に衰えがあるのではないかと客観的に推認されるでしょう。
ただし、判断能力に年齢がどれだけ影響をもたらすかは人によって違いがあるため、年齢だけを決め手として遺言能力が決められるわけではありません。
② 心身の状況や健康状態
遺言者が、遺言を作る前後でどのような健康状態にあったのかも、重要な考慮要素になります。
特に、認知症などの判断能力に関する心身状況は、遺言能力の判断に大きく影響します。「認知症が進んでおり、財産のことや家族のことなどがわからなくなってきていた」ということが客観的に立証できれば、遺言能力が否定される可能性が高まるでしょう。
この要素を判断する際に証拠として重視されるのは、遺言作成時前後の医療記録です。
病院にかかっている場合は医師のカルテや診断書、施設に入っている場合には施設での介護記録などが決め手となることも多々あります。
したがって、遺言能力を争う場合には、遺言作成前後の医療記録等の証拠を集めて、自分の側に有利な材料として主張することが重要です。
③ 遺言作成時期の言動
遺言の有効性は「遺言を作った以上、その内容と合致するような行動をとることが自然だろう」という推認に基づいています。
たとえば、遺言の内容とは正反対のことを周囲に話したり、遺言では誰かに残すはずだった資産をすぐに手放したりしていたら、遺言内容と矛盾する言動があるといえるかもしれません。
遺言内容と合致する言動がたくさん見られれば、遺言は有効だという判断に傾くでしょう。
④ 遺言の内容
「誰に遺産を残すのか」という点や「遺産の内容がどれだけ複雑か」など、遺言の内容も重要な判断要素になります。
たとえば、「生前お世話になった人に遺産を多く残したい」という遺言であれば、ごく自然な内容として受け入れられるでしょう。一方で、「生前はあまり親交が無かった人に遺産を残したい」と書かれているなど、遺言者の本心だとは考えられないような場合には、遺言の有効性が疑わしくなるでしょう。
また、実務上よく見られるのが、「遺産の内容が複雑すぎる」として無効になるケースです。たとえば、90歳を超えるような高齢者が、多数の土地や建物、何十種類もの有価証券などについてことこまかく分割方法を指定するような内容では、本当に本人がすべてを理解して遺言を作ったといえるのか怪しくなります。
実際に、公正証書遺言であっても、内容が複雑であることを理由に無効とされた判例もあるのです。
3、遺言能力が争われるケースとは?
遺言能力が争われるケースとは、一部の相続人に有利な遺言がのこされた場合です。特に、きょうだいの間で遺産の取り分にちがいがあると、争いになりやすい傾向があります。
きょうだいが親に取り入って、自分だけが得をする遺言を無理やり書かせたのではないかという疑いを持たれてしまうためです。
さらに、遺言の作成当時に認知症らしい症状が出始めていた場合にも、遺言能力が争われやすくなります。
4、遺言が無効にならないための対処法
-
(1)遺言が無効とならないためにやっておくべきこと
遺言が無効とされないためには、遺言を作成する段階で細心の注意を払っておく必要があります。
特に、きょうだいの間で取り分に差をつける場合や、遺言者が高齢である時には、後々のトラブルに備えなければなりません。
具体的には、下記のような対策をとることをおすすめします。- 遺言を書く前の本人の意思確認を録音や録画で残す。
- 遺言を作成している最中の様子を録音や録画で残す。
- 遺言作成時に、第三者の立会人を求める。
- 自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で作成する。
- 遺言の内容を決めた理由を本人の具体的な言葉で遺言の中に書いておく。
-
(2)相続人の一部から無効といわれたら
遺言能力について相続人の一部から文句が出た場合には、まずは冷静に話し合うべきです。
遺言の無効を主張する側は、多くの場合、遺言の内容に不満があるだけであって、自分の不満に対して納得がいけばそれで済むこともあります。
遺言が作成された経緯や、遺言者本人の気持ちなどが相続人の間でしっかり共有できれば、遺言に関する紛争もおさまっていく可能性があります。まずは、冷静に話し合って、すぐに訴えられるようなことがないようにしましょう。
とはいえ、相続問題では、冷静な話し合いはなかなかできないものです。
特に、相続人の配偶者が口をはさんでくると、話がこじれてトラブルになることもあります。
話し合いで解決できないときは、「遺言無効確認訴訟」という訴訟によって、裁判所に判断してもらうしかありません。
その際には、遺言作成前後の医療記録や介護記録などをすぐに取り寄せて、自分に有利な立証方法を検討していくことが重要になります。
5、まとめ
遺言は、本来、相続人の間で紛争が起きないことを願って遺言者が作成するものです。しかし、それでも、遺言が無効になってしまうことは実際にあります。そのなかでも訴訟で争われることが多い問題が、「遺言能力の有無」なのです。
遺言能力の有無に関する判断は、法的な観点はもちろん、医学的な要素も重要視されます。遺言無効の訴えを起こされた場合には、専門知識と経験をもった弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所には、遺言作成や遺言無効確認の訴えについても、豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
相続に関してお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています