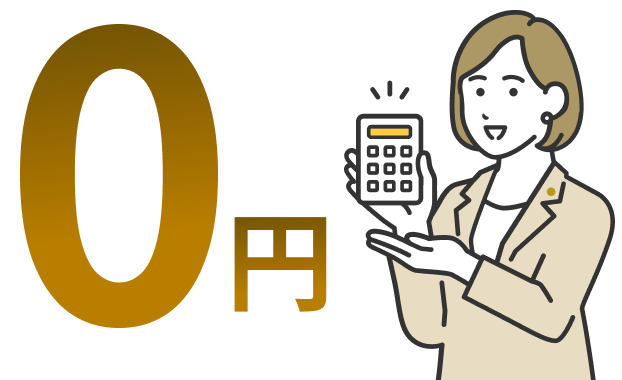遺言書を勝手に破棄されてしまった場合の対処法を解説
- 遺言
- 遺言書
- 破棄

令和2年、熊本県内では2万156名の方が亡くなって人口1000人に対する死亡率は12.3です。全国の死亡率は11.1ですから、熊本県の死亡率は全国に比べて高いといえます。
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった人のこと)が遺言書を作成していれば、誰がどんな財産をどの割合で相続するのかについて、相続人どうしでトラブルになる可能性は低くなります。
しかし、自身にとって有利な相続とするために、被相続人が作成していた遺言書が相続人によって破棄されたり改ざんされたりする場合があります。このような行為により、被相続人の意思が実現できないばかりか、相続人どうしでトラブルの原因になることもあるのです。
本コラムでは、遺言書を勝手に破棄されたり改ざんされたりした場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士が解説します。
1、遺言書の破棄・改ざん・偽造は許されない
自分が死亡したあとの相続財産の分配、事業の継承、幼い子どもに対する将来のための処置などについて、相続人のために配慮しておきたい、と考えられる方は多いでしょう。
自分の死後に、自分の遺産から生じる紛争を防止するため、遺産の分配について、最終的な意思を書面の形式であらわしたものが「遺言書」です。
社会通念として、被相続人が遺言書によって表明した意思はできるだけ尊重して、遺族や関係者たちができるだけ実現に努力すべきだという意識や感情が存在するものと考えられています。
また、このような考えから、民法においても第960条以下で、遺言書は特別なものとして保護を受けているのです。
たとえ被相続人の親族であろうと勝手に遺言書を破って捨てたり、あるいは遺言書の内容を自分に都合のいいように書き換えたり、もともと存在しない遺言書を偽造することは、許されることではありません。
そのような行為をした相続人に対しては、後述するようなペナルティーが課されます。
2、遺言書が破棄された場合の影響
遺言が実際に効用を発揮する時点では、遺言をした本人はすでにこの世に存在していません。
したがって、遺言した本人の真意を確保する趣旨から、民法では遺言の方式が規制されています。
被相続人が自分自身で作成した遺言のことを、「自筆証書遺言」といいます(民法第968条)。
被相続人が死亡して相続が発生したあとで自筆証書遺言を見つけた場合、相続人は家庭裁判所で「検認」の請求をしなければなりません(民法第1004条)。
また、遺言書に封印がされていた場合は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち合いがないと開封することができません(同条第3項)。
このような規定は、遺言書の偽造・変造を防ぐために設けられています。
そして、上記の規定に反した遺言書は無効となる可能性があります。
したがって、遺言書が破棄されていた場合は、たとえ当該遺言書のコピーが残っていたとしても、無効とされる可能性が高いのです。
3、相続人へのペナルティー
以下では、勝手に遺言書を破棄した相続人に科される、民法および刑法上のペナルティーについて解説します。
-
(1)相続欠格
民法第891条5号では、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」は、当該被相続人の相続人になることができないと規定しています。これを「相続欠格」といいます。
相続欠格は、他の相続人や被相続人が誰も気づいていなくても上記のような行為があった場合、法律上当然に発生します。
もし相続欠格に該当する行為が被相続人の生前にあった場合は、その時点で相続人になれないことが確定します。
また、被相続人が死亡し相続が開始したあとに生じた場合、相続欠格の効果は相続が開始した時点にさかのぼって発生します。
したがって、相続欠格者が事実上相続していた場合、他の相続人は当該相続欠格者に対して相続した財産を返還するように請求することができるのです。
なお、相続欠格とされた相続人に子どもがいる場合、その子どもが当該相続人のかわりに「代襲相続」することはできますので、注意が必要です。 -
(2)私用文書毀棄(きき)罪
刑法第259条では、「権利または義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と規定しています。
一般的に、遺言書は被相続人および相続人または遺言執行者の権利・義務に関する文書といえます。
したがって、遺言書を勝手に破棄した場合は私用文書毀棄罪に問われる可能性があります。
この場合における「毀棄」には、遺言書を破棄することのほか、他の相続人に見つからないように遺言書をどこかに隠してしまうことも該当します。
このような方法で他の相続人が遺言書を読むことができないようにすることは、一時的であろうと永続的であろうと、あるいは後日他の相続人に返還する意思があろうとなかろうと、刑事責任に問われる可能性があります。
なお、私用文書毀棄罪は、被害者つまり他の相続人から告訴がない以上は、刑事事件としての責任が追及されない「親告罪」となります。 -
(3)器物損壊罪
遺言書の破棄は、刑法第261条に規定する「器物損壊罪」にも該当すると考えられます。
仮に破棄された遺言書に被相続人および相続人または遺言執行者の権利・義務に関する記載がなく、単に家族へのメッセージだけが記載されていただけの場合も同様です。
刑法上、「物」とは、客観的な経済価値すなわち金銭と交換できる価値を持つものをいい、この価値が器物損壊罪など財産罪おける保護の対象とされています。
しかし、金銭と交換できる価値がなく、所有者や占有者にとってのみ価値があるものであっても、その価値が社会通念の観点から刑法上の保護に値すると認められれば保護されます
なお、器物損壊罪は私用文書毀棄罪と同様に親告罪です。また、器物損壊罪について科される刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは1000円以上1万円未満の科料です。 -
(4)有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪
勝手に遺言を書き換えた場合は、刑法第159条第1項に規定する「有印私文書偽造罪」、および同条第2項に規定する「有印私文書変造罪」に問われる可能性があります。
有印私文書とは、押印または署名がされた私人名義の文書のことです。
また、ここでいう「偽造」とは、他人名義の文書を作成権限のない者が作成することであり、変造とは既に存在している真正な文書を当該文書の名義人でない者が改ざんすることをいいます。
有印私文書偽造罪および有印私文書変造罪について科される刑罰は、3月以上5年以下の懲役です。
4、遺言書の破棄・改ざんをされたときにすべきこと
先述のとおり、遺言書の破棄や書き換えは相続欠格に該当します。
相続廃除と異なり、相続欠格には被相続人の意思に基づいた手続きは必要とされていません。
そして、当該相続人に相続欠格事由が認められれば、当然に相続権を失うことになります。
当該相続人には、相続権がないので、当該相続人を除いた上で遺産分割協議を行うことになります。
また、遺言の書き換えが疑われるときは、遺言無効確認の訴えの手続きをとることができます。ただし、遺言無効確認の訴えをするためには、「調停前置主義」に基づき、訴えを起こす前に調停をしておく必要があります(家事事件手続法第257条1項、第244条)。
5、遺言書の破棄・改ざんを防ぐためにすべきこと
一度遺言書を破棄されたり書き換えされたりすると、その遺言書は無効になってしまう可能性が高くなります。
このような事態を未然に防ぐためには、被相続人が遺言を作成した時点で公的な保護を受けるようにしておくことが大切です。
自筆証書遺言の場合、「自筆証書遺言書保管制度」という制度があります。
これは遺言者本人が作成した遺言を法務局が法的な形式チェックをしたうえで、保管してもらえるという制度です。
また、遺言書を「公正証書遺言」にしておく方法も考えられます。
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成し、その謄本を公証役場で保管するというものです。
公正証書遺言は公証人により作成されますので、法的な形式の誤りが発生する可能性は極めて低くなります。
自筆証書遺言書保管制度の活用も公正証書方式による遺言書作成も、被相続人本人が自筆証書遺言を作成し自宅で保管している場合に比べて費用がかかります
しかし、いずれも遺言書を公的な第三者が保管するため、他人に破棄されたり改ざんや隠匿されることを防げます。
もし親族の方が遺言書を自宅で保管している場合は、このようなメリットを示しながら、自筆証書遺言書保管制度を活用するか公正証書遺言に書き換えるかするように説得するとよいでしょう。
6、まとめ
遺言書に関して不明な点があったり、トラブルが生じたりしたときには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、依頼者の代理人として、トラブルの相手方となっている他の相続人との交渉や裁判上の手続きを行うことができます。
また、新たに遺言を作成する場合であっても、形式不備により無効になることを防ぐため法的な形式要件を満たすようにアドバイスをすることができるのです。
相続についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスにまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています